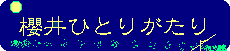「星盗人(ほしぬすびと)」
(一)
四十過ぎてはじめた日曜大工が昂じ、とうとう丸太小屋を作ってしまった。犬小屋の親玉みたいで格好がいいとはいえないが、まったく独力で自分の城がもてたのだ。満足している。なかでも特筆すべきは、ニ尺五寸四方もある二重ガラスの天窓だ。大好きなジャズを聴きながら星を見る。永年のあこがれがついに叶った。
四畳半たらずの室内は、ベッドとオーディオだけで隙間がなくなってしまった。さっそく子供みたいにベッドに跳び乗り、大の字に寝ころんでみた。
枕元の明かりを消した。目が暗闇に慣れると、南向きに傾けた天窓に冬の星々が浮かびあがった。ペテルギウス、シリウス、プロキオン、冬の大三角形だ。小屋ひとつ建てただけで、自分は生意気にも宇宙の一角を独占したのだ。こんな秘密をだれに打ち明けよう? 歓びに息苦しささえ覚えたその時だった。
上の窓枠からにゅっと茶色い手が伸びて、素早くプロキオンをつかみとった。
思わず「わっ」と叫び声をあげたら、だだだだっと音をたて何か窓の傾斜をすべり落ちてきた。窓枠と屋根材との段差に引っかかると、それは癇癪を起こしたような勢いでガラス面を引っ掻きはじめた。
手探りで点した明かりに照らし出されたのは、短い灰色の毛におおわれた、鼠の化け物のような生き物だった。「こりゃ、いったいなんだ」恐怖をひとり言で紛らわしながら、その姿形を凝視した。
光に目が眩んだのか、それはすぐにおとなしくなった。身体の両側面に張る薄い皮膜のおかげで彼の正体を知ることができた。むささびだ。
私は上着を羽織り、小屋の外へと飛び出した。軒下に置いてあった脚立を立て、竹箒を片手に屋根が見える高さまで登ってみた。
襟巻にすればさぞ暖かそうな尻尾が、軒先から四五十センチというところで揺れていた。腕をいっぱいに伸ばし、箒で屋根に弧を描いた。窓から払いのけられたむささびは、ブーメランのように回転しながら軒下に墜落した。
地面にぶつかった衝撃で、彼のくわえていたプロキオンが飛びだして、きらきら火花をまき散らしながら脚立の足場まで転がってきた。それを拾いあげ、地にうずくまる星盗人の前に私は仁王立ちした。
「獣の分際で星を盗むとは、なんたる不心得ものだ。しかも可哀想なことに、小犬の心臓を(プロキオンは、小犬座の胴体部にあたる)。これだからロマンチシズムを解さぬものは困る」
ぶるぶると身を震わせながら、むささびは黒真珠のようなまなこで私を見上げた。がぜん、か弱いものに対する哀れみが胸にこみあげ、また獣相手に一席ぶったことが気恥ずかしくなってきた。
「まあいい。おまえにあれこれ諭したところで、なんの得にもならないし。星は私が戻しておくから、おまえは森に帰りなさい」
「しっ、しっ」と追い払う手つきをしたが、彼はまったく動こうとしない。箒の柄で軽く突いても、冷たい土にへばりついたまま、じっと・・・・・・いや、動けなくなったのはこちらの方だった。ふたたび彼と目があって、その瞳の崇高なきらめきに魅入られてしまったのだ。気がつくと、私は膝が抜けたようにしゃがみこみ、ひくひく動く彼の鼻先にプロキオンを差し出していた。
(二)
月は私を追い、私はむささびを追いかけた。路ぞいの木立をまつり縫う光をたよりに、女房の買物自転車を走らせた。
とはいっても、彼の飛翔のテンポは意外なほどのんびりしていた。木から木へ飛び移っては枝の上で一休み。それから幹を登って、より高い枝に踏み切りの場をもとめ、慎重に次の目標を見定めてやっとまた飛び立つ。
そのため途中で見失ったり、息がきれたりする心配はなかったが、運動で身体が火照ることもなく、時が経つとともに底冷えが身にしみてきた。
下の里が近づくにつれて山裾が左右にしりぞき、田畑が扇状にひろがりはじめた。むろん路ぞいの木立もまばらになり、むささびのペースはさらに落ちていった。それからしばらく行って、用水の上に架かる短い橋のたもとで、ついに樹木の列が途切れた。
むささびは、あきらかに困惑した素振りをみせていた。顎が外れそうなほど歯を鳴らしながら、私は彼の動きを注視していた。
さんざんためつすがめつしたすえ、彼はくるりと向きを変え、後ろの木に対して身がまえた。いったん元来た路を引きかえし、山裾の林に沿って大回りするつもりなのだ。ただでさえ凍え死に寸前の私は、あわてて自転車のカゴを指して叫んだ。
「おおい、ここに乗せてやるから降りてこい!」
むささびは私を見下ろし、くりくりと首をひねった。そこでいっそう大げさに、カゴを指す動作をくり返した。
「はやく降りてこい。ここに入れていってやる」
この呼びかけが通じたのか、むささびは枝を離れ、幹をつたって地面まで滑り降りてきた。
「ありがとう、信じてくれたんだな」
私は彼を抱きあげ、自転車の前カゴに入れてやった。
「さあ、どこに行きたいんだい」
答が返るはずはない。ただまっすぐ前を見ているから、このまま進めばいいのだろう。奪われた体の熱を取り返すため、全力でペダルをこぎだした。
むささびがくわえているプロキオンのおかげで、前方は十二分に明るい。ダイナモを切ったらペダルの踏み応えが軽くなり、自転車はさらに加速した。手や顔の皮膚は風に打たれて腫れあがり、分厚い革をかぶったように痛さも何も感じなくなった。こうなるともう腹の中がかっかと燃え出して、十里二十里でも走り続けてやれ、という勇ましい気持ちさえ湧いてきた。
下の里の家々は、広い田畑の間に点在している。すでにどの家も雨戸を閉めきった中、一軒だけこうこうと灯りが洩れていた。家屋の側には、巨大な影がそびえている。
その家が見えてきた頃から、むささびが急に落ち着かなくなった。しきりにカゴから身を乗り出そうとする。危なっかしくてしかたがないので、道端に自転車を停め、彼をカゴの中からとりあげた。
「あそこに用事があるんだな」
むささびは懸命に、前方の灯りに向かって小さな首を伸ばしている。
「それじゃ、このまま歩いていこう」
星とむささびを抱いた私は、残り半キロばかりの路を徒歩でいそいだ。
(三)
寒椿の紅がこぼれる垣根の前には、黒塗りの車が停めてあった。それを横目でうかがいながら、静かに木戸をくぐり前栽の中に忍び入った。
まず私を驚かせたのは巨大な影の正体、それは、幹の太さが二抱えほどもあるエノキの大木だった。その偉容をさほど大きくない母屋と比べてみると、家が樹に寄生しているかのような錯覚におちいる。
天に向かって伸びあがる七頭蛇=ヒュドラのような枝ぶりを唖然と見上げる隙に、むささびが腕をすり抜けた。彼はたちまちエノキの幹を駆けのぼり、軒よりもわずかに低い枝先にふたたび姿をあらわした。
家の中は、けっこうにぎやかな様子だった。人の声に加え、鈴やガラガラなど、子供の玩具の音がひっきりなしに鳴っていた。
縁側のガラス戸は三段に仕切られ、下の二段には磨りガラスがはまっている。そのため、普段の目の高さでは内をうかがうことができない。
「せっかく運転手になってやったのに、おまえだけ楽しむなんてずるいぞ」
近くの庭石を足がかりにして、私もいちばん低い枝によじのぼった。こわごわと腰を浮かせば、いちばん上の透き通しのガラス越しに、柔らかな白熱電球の光に照らされた座敷の有様が見えてきた。
座敷の真ん中に小さな男の子が寝かされていた。彼をはさんで、座敷の上り口側には白衣を着た医師と看護婦、反対側には、年のころ三十前後と思われる夫婦と、祖母らしき老女が座っていた。
医師は血相を変え、はだけた子供の胸にマッサージをほどこしている。母親は夫の制止もかまわず、鳴り物の玩具を振りながら子供の名を呼んでいる。老女は背中を丸めて合掌し、神仏への祈りを唱えているらしい。
とても見ていられる光景ではなかった。私は枝に腰を降ろすと、騒ぐ心を鎮めるため、懐から取り出した煙草に火をつけた。けれど家の中が見えなくなるとかえって、母親の呼び声が私の胸を緊めつけた。
「もう堪えられない。先に帰るぞ」
そう言った直後、母親の号泣がガラスを突き抜けてきた。たまらず耳をふさぎ、かぶりを振らざるをえなかった。
と、不意に木肌のこすれる音がして、頭上の枝がぐんとしなった。私の目線は、その先端にいるむささびに向けられた。彼は精いっぱい身体を弓なりに反らし、くわえつづけていた星を宙に放った。
やや緑色を帯びた軌跡を描いてプロキオンが切妻屋根の棟に達した。同時に、もうひとつの白い光が、建物から垂直に浮かびあがった。
二つの光は、しばらく戯れ合うように円く追いかけっこをしていたが、やがてプロキオンが導くように先に立ち、天空へと昇りはじめた。
「おまえはあの子のために」
「うん、そうだよ」と言いたげに、むささびは私を見つめかえした。
心やさしい彼は、幼い魂が迷ったり寂しがったりしないよう、友となり案内役となる星を連れてきたのだ。
ふたたび夜空を見上げると、二つの光はぐんぐんと速度を増して遠ざかり、ついには背景の暗黒に吸いこまれていった。
「よかったな、あの子は無事天国にたどり着けそうだ」と言って目線を戻した時、すでにむささびの姿は樹上に無かった。別段おどろきはしなかった。けれど、自分もここにいてはいけないという気がして、あわてて枝から飛び降りた。
背中に「ごめんね、ごめんね」という母親の声を聴きながら、私はエノキの影に覆われた庭をあとにした。
* * *
また寒さと闘いながら家路をいそいだ。
ふと自転車を停めて天を仰ぐと、プロキオンはいつもと変わらぬ緑白の光を放ち、大きく西に傾いた大三角形の一角に座していた。
そして、その隣に寄り添う、見覚えない小さな星を見つけた時、「あなたが謝るべき不幸など、あの子には無かったはずですよ」という呟きが、唇からしぜんにこぼれた。
了
|